今こそ必要!病院ができる業務効率化の具体策とポイント
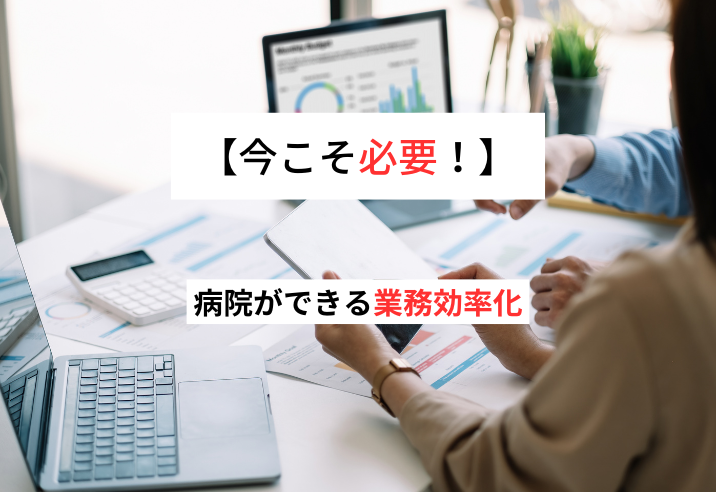
近年、医療現場では業務の効率化が注目されています。
そのなかで、「なぜ業務効率化が必要なのか」「どんな方法があるのか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、病院業務の効率化が必要とされる背景と具体的な方法について、わかりやすく解説します。
病院の業務効率化に関心のある医療関係者の方は、ぜひご覧ください。
病院業務効率化の必要性と背景
業務効率化への取り組みは、病院経営や現場運営に欠かせないものとなっています。
なぜ業務効率化が求められるのか、必要性と背景について解説します。
医療現場の人手不足
現在、医療現場では深刻な人手不足が社会的な課題となっています。
少子高齢化が進み、医療を必要とする患者さんは年々増加している一方で、医療従事者の数はそれに追いついていないのが現状です。また、働き方改革や労働条件の厳しさ、都市部への人材集中も、人手不足の要因となっています。
医師や看護師はもちろん、病院や診療所の運営を支える医療事務職の人手不足も深刻です。
医療事務職の有効求人倍率は全国平均で約2倍と高い水準にあり、求職者1人に対して約2件の求人がある状態です。これは、医療機関が必要とする医療事務職員を十分に確保できていないことを意味します。
人手不足は、サービスの質の低下や職員の離職リスクの増大といった問題にもつながり、病院経営や現場運営に深刻な影響を及ぼします。
そのため、限られた人材で効率的に業務を進める工夫が必要となっており、業務効率化が注目されているのです。
参考:職業情報サイトjobtag「医療事務」‐厚生労働省
DX化・自動化の重要性
上記の課題を解決するために、病院ではデジタル技術の導入が進んでいます。これがいわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)です。業務を自動化することで、人手不足を補い、職員の業務負担を軽減するとともに、サービスの質を向上させることが可能になります。
特に、受付・診察案内・会計といった患者さんの対応業務では、多くの病院でDX化が進んでいます。
これらの業務は一人ひとりの患者さんへの対応数が多く、また正確さやスピードが求められるため、デジタル技術の導入効果が大きい分野です。
DX化を推進することで、病院の経営基盤が安定し、職員にとって働きやすい職場環境が整い、離職防止にもつながります。そして、患者満足度の高い病院づくりが実現できるのです。
また、データの蓄積・活用が可能になることで、さらなる医療サービスの質の向上や経営の効率化、新たなサービスの開発にもつながります。
病院の具体的な効率化策
病院業務の効率化は、現場の負担を軽減し、患者さんへの医療サービスを維持・向上させるために重要です。ここでは、病院で実践されている具体的な効率化策について、主な取り組みをいくつかご紹介します。
受付業務の自動化
病院の受付業務の自動化とは、従来職員が手作業で行っていた受付業務を、自動受付システムを使って自動化・効率化することです。患者さんが診察券や保険証、マイナンバーカードを機械にかざすだけで、受付の手続きが完了します。
自動受付システムは、電子カルテやレセプトシステムと連携するため、患者情報の自動登録・管理が可能です。導入によって、職員は患者対応や緊急時のサポートなど、より重要な業務に集中できるようになります。
診察案内・会計案内の表示システム
診察案内・会計案内の表示システムは、待合室モニターに診察の順番や会計準備完了のお知らせを表示できるシステムです。患者さんは自身の順番をひと目で把握できるため、職員への問い合わせや確認をすることなく待つことができます。その結果、受付や会計窓口の混雑が解消でき、職員の負担も大幅に軽減されます。
さらに、多言語対応や音声案内機能を備えることも可能で、外国人・高齢者・視覚障がいのある方への配慮としても効果的です。
会計業務の効率化
病院の会計業務は、診療報酬の計算、保険適用の確認、領収書や明細書の発行など、煩雑で正確性が求められる業務です。人手での対応が中心であり、患者さんを待たせる要因となることも少なくありませんでした。そこで効果的なのが、自動精算機の導入です。診療内容に基づいた会計データが電子カルテ(レセコン)から自動連携され、患者さんは自動精算機でスムーズに支払いを済ませることができます。
現金・クレジットカード・電子マネー・QR決済など、多様な支払い方法に対応することで、患者さんの利便性も高まります。
自動精算機の導入メリット
自動精算機の導入は、病院の会計業務だけでなく、病院全体の業務効率化に大きなメリットをもたらします。
・会計待ち時間の短縮
患者さん自身で会計を済ませられるため、会計窓口での混雑や待ち時間を大幅に削減できます。
・職員の負担軽減
会計業務が自動化されることで、職員は他の対応に集中できるようになります。
またお釣りの差異がほぼゼロになり、締め作業が大幅に楽になります。
・人的ミスの防止
会計金額の計算や釣銭の間違いといったヒューマンエラーが減少し、トラブルを予防できます。
・感染症対策
職員と患者さんの双方の接触回数を減らせるため、感染症対策にもなります。
自動精算機は病院の運営効率だけでなく、患者さんにとっても安心で快適な受診環境を整えることができます。
自動精算機導入の注意点
自動精算機の導入にはメリットがある一方で、いくつかの注意点があります。
ここでは、自動精算機導入の注意点を紹介します。ぜひ参考にご覧ください。
職員への教育・研修の実施
自動精算機の基本的な操作方法や、トラブル発生時の対応方法を職員が理解することで、現場での混乱を防ぎ、スムーズな運用が可能となります。
導入時には、操作説明会や実機を使ったトレーニングを行い、職員が自信を持って対応できる体制を整えましょう。
高齢者や機械操作に不慣れな患者さんへの配慮
自動精算機の操作は、患者さんによってはスムーズにできず、ストレスに感じることもあります。
そのため、操作に戸惑う患者さんをサポートできるよう、職員が補助できる体制を確保することが重要です。使い方の案内表示や音声ガイド、患者層に応じて多言語対応なども検討するとよいでしょう。
導入後のメーカー(販売業者)のフォロー体制
自動精算機を導入した後のメーカーのフォローや保守体制の確認も重要です。
信頼できるメーカーを選び、定期的なメンテナンスやトラブル時の迅速な対応など、アフターサポートを受けられることを事前に確認しておく必要があります。
また、停電や通信障害などの非常時に備えたマニュアルや対応手順も整えておくと安心です。
まとめ
病院の業務効率化は、医療現場全体を安定した運営に変え、患者さんへのサービスの質を維持・向上させるために必要な取り組みです。深刻化する人手不足の中、DX化や自動化の推進は病院経営の安定や、現場職員の働き方改革に直結しています。
受付業務の自動化、診察案内・会計案内の表示システム、そして自動精算機の導入といった具体的な施策を組み合わせることで、病院の業務は大幅に効率化され、職員の負担軽減と患者さんの満足度向上の両立が実現できます。
病院の自動精算機は、ぜひ「Robo Clerk(ロボクラーク)」をご検討ください。
弊社ではただ設置するだけでなく、現場で円滑に活用いただけるよう導入後のフォローも徹底しています。稼働後も法令改正への対応や業務改善に関するご相談など、医療機関の皆さまを長期的にサポートいたします。 自動精算機の導入や運用に関するご質問・ご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
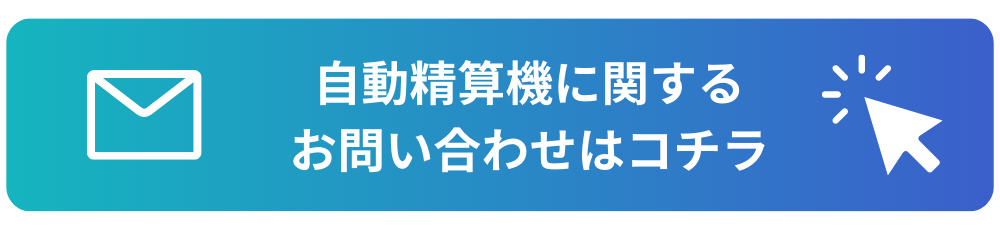
この記事の執筆者
株式会社APOSTRO
マーケティング担当T.O
約5年間の海外暮らしを経験し、某広告代理店で海外の現地法人責任者となる。部分最適に拘る日本の生産性向上に疑問を持っていたところ、「働き方を変える」というテーマを熱く語るAPOSTROに共感し、自らが社会実装役になることを決意し参画中。
自動精算機の導入と合わせてセキュリティ対策を検討したい方は
是非お問い合わせフォームからお問い合わせお待ちしています。
