要注意!病院の自動精算機を選ぶ上で大切な7つのポイント
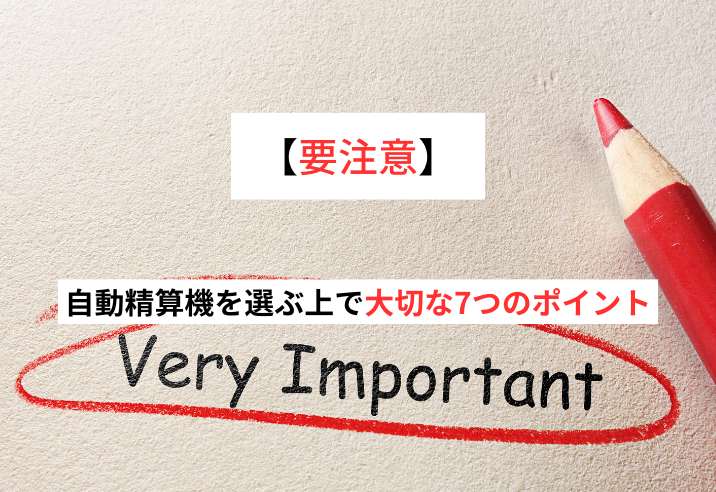
近年、病院では自動精算機の導入が急速に進んでいます。
自動精算機は、患者さん・職員の双方にとって多くのメリットがあります。
ただし、「なんとなく便利そうだから」といった理由で導入を進めてしまうと、期待した効果が得られなかったり、実際の業務に合わなかったりするリスクもあります。
本記事では、自動精算機の導入で後悔しないために押さえておきたいポイントを、「導入目的の明確化」から「機種を選ぶ際の7つのポイント」まで詳しく解説します。
まずは導入目的を明確に
自動精算機の導入で後悔しないためには、まずは導入目的を明確にすることが重要です。自動精算機の導入は、業務効率の向上、患者さんの待ち時間短縮、職員の負担軽減、感染症対策といったさまざまなメリットがあります。
しかし、導入の目的や期待する効果を定めておかないと「思ったような結果が得られなかった」「もっと別の機種にすればよかった」という声につながりかねません。
自動精算機に何を求めているのかを検討し、その目的に合った製品選びを行うことが、失敗しない導入につながります。
失敗しない!自動精算機選びの7つのポイント
自動精算機に期待する効果を得るためには、どのような自動精算機を選ぶかが重要です。
自動精算機を選ぶための7つのポイントをご紹介します。
①レセコン・電子カルテとの連携
自動精算機を選ぶ際は、すでに導入しているレセコン・電子カルテとの連携が可能かを確認しましょう。連携に関する情報は、メーカーによっては非公開の場合が多く、事前に問い合わせが必要となることが少なくありません。また、連携が可能な場合は、連携の方法も確認が必要です。
主な連携方法は次の2つがあります。
1.データ連携
電子カルテの患者IDと自動精算機をオンラインで直接結び付ける方法です。
【メリット】
保険証の違いや加算の変更によって請求金額が変わった場合でも、速やかに正確な会計処理が可能です。どの患者さんがどのタイミングで会計を行ったかが記録に残ります。
再来受付や領収書・明細書の発行もスムーズに行えます。
【デメリット】
メーカーが指定する機種や機器しか選べない場合があります。また、バーコード連携に比べて導入費用が高くなる傾向があります。
2.バーコード連携
受付で会計金額情報の入ったバーコードを患者さんに渡し、そのバーコードを自動精算機で読み取って会計を行う方法です。多くの場合、バーコード情報は領収書に印字されていることが一般的です。
【メリット】
バーコードを読み取って会計ができるため、比較的低コストで導入できる場合があります。
【デメリット】
誰が会計を行ったかの記録が残らないため、締め作業や請求金額の修正が必要になった際に時間がかかることがあります。
データ連携とバーコード連携を比較すると、データ連携の方が機能面で優れており、利便性も高いのが特徴です。
予算に余裕がある場合は、医療機関で使用している電子カルテやレセコンとデータ連携が可能な自動精算機を選ぶことをおすすめします。
②患者さんが操作しやすい
自動精算機を選ぶ際、患者さんの「操作のしやすさ」は重要なポイントです。
操作性が悪いと、患者さんが戸惑ってしまい、結局職員がサポートに入る必要が出てきます。
それでは、せっかく自動精算機を導入しても、業務効率化やスタッフの負担軽減といった目的を十分に果たせなくなってしまいます。
特に、高齢者の患者さんが多い診療科や医療機関の場合、画面の文字サイズやボタンの大きさ、操作手順のシンプルさなどをしっかり確認することが大切です。
実機に触れたり、デモ機での操作体験を通して、患者さんがどの程度スムーズに使えるのかを事前に確認しましょう。
また、弊社の自動精算機『Robo Clerk』では、医療機関の皆さまに安心して導入をご検討いただけるよう、オンラインデモや実機デモも対応しています。
デモを通じて操作画面や流れを確認できるため、患者さんの特性や自院のニーズに合った機種選びにお役立てください。
③キャッシュレス決済対応
近年、クリニックや病院においても「キャッシュレス決済」のニーズが高まっています。
これまでは多くの患者さんが現金で支払われていましたが、政府によるキャッシュレス決済普及の後押しや、社会全体のキャッシュレス化の流れにより、医療機関でもその需要は着実に増えています。
高齢者の患者さんが多い診療科目では、現金決済だけでも当面は大きな問題はないかもしれません。
しかし、将来的な患者層の変化や利便性向上を見据えると、キャッシュレス決済に対応しておくことは重要と言えます。
もし現在、自動精算機の導入を検討しているのであれば、この機会にキャッシュレス決済機能の導入も併せて検討してみてはいかがでしょうか。
キャッシュレス決済に対応することで、現金を持ち歩かない患者さんの満足度向上や、現金管理業務の負担軽減にもつながります。
弊社の自動精算機『Robo Clerk』も、オプションにはなりますが各種キャッシュレス決済に対応しています。
対応可能なキャッシュレス決済の例
- クレジットカード決済:主要なブランドに対応
- 電子マネー決済:交通系IC、WAON、QUICPay
- QRコード決済:AliPay、WeChatPay、銀聯QR、JKOPAY、PayPay、d払い、auPAY、メルペイ、J-Coin Pay、楽天ペイ
今後ますます進むキャッシュレス化に備え、柔軟に対応できる自動精算機を選ぶことが、患者さんにとっても、医療機関にとっても大きなメリットになるでしょう。
弊社が医療機関向けに提供するキャッシュレスサービスACS(APOSTRO Cashless Service)はクレジット(VISA / Mastercard)の決済手数料率が業界最安レベル!
詳細はお問合せのうえ、ご確認ください。
④お釣りの補充が少なく済むか
自動精算機を頻繁に操作するのは職員となります。
そのため、職員にとっての操作性やメンテナンスのしやすさも、自動精算機選びにおいて重要なポイントとなります。
操作のなかでも、職員が手間と感じるのが「お釣りの補充作業」です。
導入後の職員の負担を軽減するためには、お釣りの補充作業をできるだけ減らせる機種を選ぶことが大切です。
自動精算機を選ぶ際、以下の2点をチェックすることをおすすめします。
1.硬貨・紙幣ごとの収容枚数を確認する
自動精算機が収容できる硬貨と紙幣の数を事前に把握しておきましょう。
収容枚数が多いほど、お釣りがなくなる頻度が減り、補充の回数を少なくすることができます。
2.硬貨・紙幣が「循環式」かどうかを確認する
お釣りの補充作業の負担を大幅に軽減できるのが、硬貨や紙幣を自動で再利用する「循環式」の自動精算機です。
循環式であれば、患者さんが支払った現金がそのまま次のお釣りとして使われるため、効率的に運用でき、補充作業の手間が格段に減ります。
弊社の自動精算機『Robo Clerk』は、釣銭機一体型のため紙幣や硬貨は循環式になっており、お釣りの補充作業の負担を大幅に軽減します。
「職員の負担をできるだけ減らしたい」「日々のメンテナンスに時間を取られたくない」という医療機関の皆さまは、ぜひ一度ご相談ください。
⑤設置スペースやデザインの適合性
自動精算機を導入する際、設置スペースと機器のデザインが院内環境に適しているかどうかも重要なポイントです。
自動精算機が動線を塞いでしまうと、患者さんも職員もストレスの原因になってしまいます。
また、機器の外観やデザインが、院内の雰囲気と調和しているかどうかも確認しましょう。
弊社の自動精算機『Robo Clerk』の本体サイズは以下のとおりです。
本体サイズ(設置台・ローレル釣銭機含む)
- 高さ:119.6cm
- 幅:49cm
- 奥行き:62cm
本体サイズ(サイドパネル含む)
- 高さ:135cm
- 幅:53.7cm
- 奥行き:64cm
また、『Robo Clerk』は清潔感と親しみやすさを意識したデザインを採用しており、どのような医療機関にも自然に溶け込むよう設計されています。
シンプルながら洗練されたフォルムによって、院内の雰囲気を損なうことなく設置が可能です。
⑥初期費用・ランニングコスト
自動精算機は安価な買い物ではないため、導入のメリットだけでなく、初期費用やランニングコスト、購入方法なども慎重に検討しましょう。
自動精算機には、導入時にかかる初期費用と、導入後に継続的にかかる保守費用があります。
一般的な病院向けの自動精算機の場合、目安として以下のような費用感が想定されます。
※以下の価格は参考です。
Robo Clerkのお見積りはお問合せください。
- 初期費用(導入時のみ): 約500万円〜600万円
- 保守費用(月額): 約3万円〜5万円
自動精算機の償却期間は通常5年(60か月)程度で計算されることが多いため、月々の負担額は次のように概算できます。
(初期費用600万円÷60か月)+ 保守費用4万円 ≒ 月額14万円
選ぶ機種やオプション、決済機能の内容によって費用は変わりますので、詳細な見積もりを確認することが大切です。
また、自動精算機は購入だけでなくリースでの導入も可能です。
リース契約にすることで初期費用の負担を抑え、経費の計画が立てやすくなります。
購入とリースの条件や総額を比較し、自院に最適な導入方法を検討しましょう。
⑦導入後のサポート体制
自動精算機の導入において、導入後のサポート体制は長く安心して運用していくために欠かせないポイントです。自動精算機は精密機器であるため、どれだけ高性能な機種であっても、長期運用の中では稀に不具合やトラブルが発生する可能性があります。
精算機にトラブルが起きると、その間は受付で職員が会計対応を余儀なくされ、業務が滞ったり、患者さんをお待たせしてしまったりと、院内業務に大きな影響が出てしまいます。
だからこそ、不具合発生時にどのような対応が受けられるのか、どこまでサポートしてくれるのかを事前に確認することが大切です。
確認すべき主なポイントは次のとおりです。
- 不具合発生時の電話サポートの有無・対応時間
- リモートサポートによる迅速な遠隔対応が可能か
- 必要に応じた現地訪問対応がどこまでカバーされるか
- 土日・祝日や夜間対応の有無
弊社では、土日も対応可能な専用サポートダイヤルを設置し、迅速で的確なサポートを提供しています。まずは電話で状況を伺い、リモートによるトラブル解決を試みます。
問合せの7割はリモートで解決しますが、それでも解決できない場合は現地訪問による対応を実施しています。
万全のサポート体制で、医療機関の皆さまが安心して自動精算機をご利用いただけるよう全力でサポートしています。
まとめ
自動精算機を導入する際は、「なぜ導入するのか」「導入によってどんな効果を期待するのか」を明確にし、その目的に合った機種を選定することが重要です。
弊社が提供する自動精算機『Robo Clerk(ロボクラーク)』は、これらのポイントを網羅した仕様で、多くの医療機関に導入いただいております。
操作性や機能性、サポート体制まで幅広く対応しております。
導入前のご相談や現地調査も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
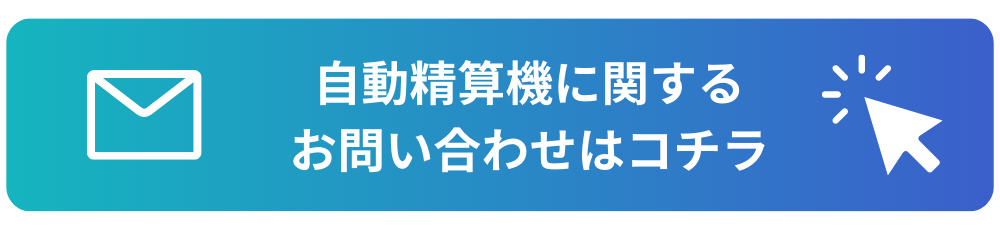
この記事の執筆者
株式会社APOSTRO
マーケティング担当T.O
約5年間の海外暮らしを経験し、某広告代理店で海外の現地法人責任者となる。部分最適に拘る日本の生産性向上に疑問を持っていたところ、「働き方を変える」というテーマを熱く語るAPOSTROに共感し、自らが社会実装役になることを決意し参画中。
自動精算機の導入と合わせてセキュリティ対策を検討したい方は
是非お問い合わせフォームからお問い合わせお待ちしています。
