どうなる病院経営?2026年度診療報酬改定をめぐる議論が本格化
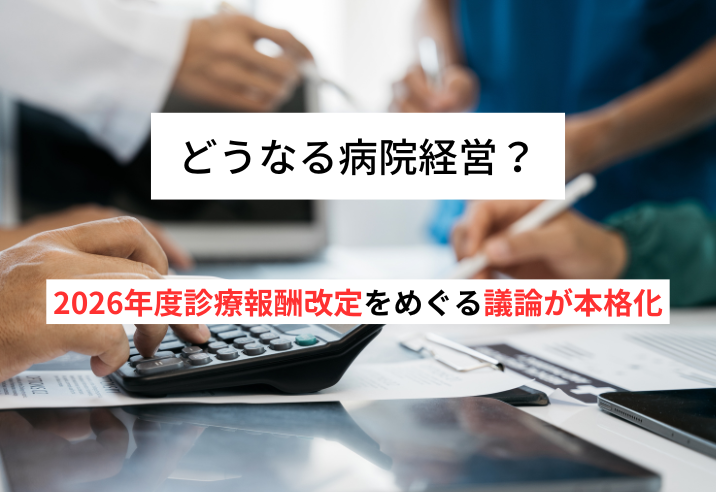
現在、2026年度の診療報酬改定に向けた議論が本格化しています。
今回の改定は、物価の上昇や人件費の高騰による病院経営の課題が重なる中で行われることから、例年以上に注目されています。
本記事では、病院を取り巻く経営環境の変化、病院団体と政府の主張、そして経営改善に向けた具体的な取り組みについて解説します。
診療報酬改定とは
診療報酬改定は2年ごとに行われ、医師や看護師が提供する医療行為や、薬剤・検査・処置に関する報酬の水準を見直す仕組みです。
議論が行われるのは中央社会保険医療協議会(中医協)で、厚生労働省、財務省、学識経験者、医療団体、保険者団体、患者代表などが加わり、社会全体のバランスを見ながら調整されます。
なお、2024年度改定は、全体としてマイナス改定(報酬ベースが下がる)となり、現場からは「医療機関の経営実態を十分反映していない」という不満が多数上がりました。
マイナス改定の影響もあり、医療機関の赤字割合は全国的に増加しています。
2026年度改定は、コロナ禍終息後、医療提供体制の変化を踏まえた初の大型改定となっており注目されています。
病院を取り巻く経営環境の変化
近年、病院の経営環境は大きく変化しています。
エネルギーコストや物価の上昇、人件費の高騰、そして医療機関の赤字経営の拡大など、課題は深刻です。以下にて順に解説していきます。
エネルギーコストと物価の上昇
病院経営に大きな打撃を与えているのが、エネルギーコストと物価の上昇です。
電気代やガス代の光熱費は全国的に値上がりしており、空調や医療機器を常に稼働させる病院では、その負担がとても大きくなっています。さらに、輸入に頼る医薬品や検査機器の価格も上昇しています。
病院は一般の企業のように価格を自由に上げることができないため、コストの増加を患者さんの支払いにできず、経営はますます厳しい状況に追い込まれています。
人件費の高騰
さらに大きな問題となっているのが、人件費の高騰です。
医師や看護師だけでなく、放射線技師や臨床検査技師といった専門職でも人手不足が続き、病院は賃金を上げて待遇を改善しなければ、人材の確保が難しくなっています。
特に地方の病院では、求人を出しても応募が集まらないケースが増えています。
看護職員を対象とした「看護職員処遇改善評価料」という補助もありますが、対象が限定されているため十分ではありません。
そのため、診療報酬に人件費の上昇分を反映させることへの期待が高まっています。
赤字経営が常態化する自治体病院
コスト増や人件費の上昇は、医療機関の経営数値に表れています。
公益社団法人全国自治体病院協議会がまとめた「会員病院の令和6年度決算状況調査の結果」によると、有効回答のあった657病院のうち、経常損失を出した病院は86%に達しました。
さらに、診療報酬を中心とした本業の収支を示す「医業損失」では95%もの病院が赤字という結果でした。
つまり、診療報酬収入だけではほとんどの自治体病院が赤字に陥っており、補助金などを含めても経営を維持できない病院が大半を占めている実態が浮き彫りになりました。
参考:会員病院の令和6年度決算状況調査の結果‐公益社団法人全国自治体病院協議会
2026年度診療報酬改定をめぐる病院と政府の主張
病院経営をめぐる厳しい状況を背景に、2026年度診療報酬改定に向けた要求と論点が明確になりつつあります。
病院団体は診療報酬の大幅引き上げを求めていますが、政府は財政の観点から慎重な姿勢です。
ここでは、それぞれの立場と主張を解説します。
病院は大幅な引き上げを求める声
厳しい経営環境を受けて、病院団体は診療報酬の引き上げを強く求めています。
日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本慢性期医療協会、全国自治体病院協議会の6団体が合同で行った調査では、「十分な賃上げや待遇改善ができなければ、人材の流出が進み、地域医療が成り立たなくなる」と危機感を示しました。
また、若い医師や看護師が、待遇の良い都市部や他業種に流れてしまう傾向もあります。
さらに、経営難により病院が閉院に追い込まれたり、診療科を減らさざるを得なくなるケースも懸念されています。
政府は慎重な姿勢
政府は基本的に、医療・介護・年金といった社会保障費の増加をできるだけ抑える方針をとっています。
そのため「限られた医療費をどう分けて、効率的に使うか」が大きな課題になっています。
財務省は特に厳しい立場を示しており、「医療費は今後も増え続ける見込みがあるため、診療報酬を安易に引き上げれば国の財政を圧迫する」として、引き上げには慎重です。
さらに「ICTの活用や業務の効率化で病院経営を改善すべきだ」と主張しており、診療報酬の大幅な引き上げを求める病院側と対立しています。
このため、次の診療報酬改定でも「全体を一律に増やす」のではなく、必要性の高い分野や効率化が難しい分野に重点を置く、メリハリのある配分が行われる見通しです。
病院経営改善の具体的な取り組み
病院経営の現場では、人件費高騰への対応としてICTの活用や業務効率化が求められています。
デジタル技術やシステムを導入することで、医療従事者の事務的な負担を軽減し、運営コストを削減するだけでなく、診療の質や患者サービスの向上も期待されています。
以下では、その代表的な取り組みをご紹介します。
電子カルテ・電子処方箋
病院業務のデジタル化の中でも、最も基本となるのが電子カルテや電子処方箋です。
クラウド上で管理すれば、院内だけでなく地域の医療機関ともデータを共有可能です。
医師や看護師は必要な情報をすぐに検索でき、二重入力や記録漏れも防止できます。
薬局側も処方内容を正確に受け取れるため、調剤ミス防止にもつながります。
オンライン診療・予約システム
患者さんが自宅からスマホやパソコンを使って、診察を受けられる仕組みです。
糖尿病や高血圧など、定期的なフォローアップが必要な慢性疾患患者に特に有効です。
また、診療予約や問診をオンライン化すれば、電話対応や窓口対応の負担が減り、受付スタッフの人員削減や待合室の混雑緩和にも効果があります。
自動精算機
自動精算機は、患者さんが診察後に自分で会計処理を行える端末です。
会計の待ち時間を解消できるうえ、スタッフによる現金計算や釣銭の間違いも減らせます。
クレジットカードや電子マネーに対応した機器も増えています。
その中でも注目されているのが病院向けの多用途端末「Robo Clerk」です。
再来受付や会計を1台でこなすRobo Clerk。病院に必要な機能を絞り込むことで導入コストを抑え、現場で使いやすい仕様を実現しました。
診察券をかざすだけで再来受付ができ、案内表示板とのシステム連携により診察や会計の待ち状況も確認できます。
キャッシュレス決済にも対応しており、高齢の患者さんでも直感的に操作可能。
Robo Clerkの導入で、窓口スタッフの業務負担は大幅に軽減され、人件費高騰への対応にも役立ちます。
まとめ
2026年度の診療報酬改定に向けた議論では、病院側が「報酬を引き上げなければ人材が流出し、地域医療が守れない」と訴える一方で、政府は「財政負担を考えると、まずは効率化で対応すべきだ」と慎重な姿勢を取っています。
人件費高騰の解決策として注目されているのが、ICTの導入や業務の効率化です。
多用途端末の「Robo Clerk」は再来受付から会計までを1台で対応し、スタッフの負担を減らしながら、医療の質や患者サービスの向上につなげることが可能です。
診療報酬改定の動きに注視しながら、ICTや業務改善を取り入れ、これからの病院経営を守り、地域医療を支える力となっていきましょう。
