2026年を目途に出産費用が無償化へ!病院・産院ができる備え

2026年を目途に、出産費用の原則無償化が本格的に進められる見通しです。
妊産婦にとっては大きな経済的支援となる一方で、出産を取り扱う医療機関では新たな課題への対応が求められます。本記事では、無償化の対象となる出産費用の概要と制度変更の背景、無償化によって想定される病院側の課題、そして今から取り組める備えについて詳しく解説します。
H2:無償化の対象は「標準的な出産費用」
現在の制度では、帝王切開など一部のケースを除き、通常の出産(正常分娩)は病気やけがに該当しないため、公的医療保険の適用外となっており、出産費用は自己負担です。そのため、出産育児一時金として50万円が支給される形で、費用の一部が補助されています。
しかし、実際の出産費用は地域や医療機関によって大きく異なり、50万円を超えるケースも少なくありません。こうした現状を受けて、新たな方針では「標準的な出産費用」について自己負担をゼロにすることを目指し、公的医療保険の適用対象とする方向で制度設計が進められています。標準的な出産とは、安全に出産するために必要な基本的な医療やケアを指します。
一方で、豪華な食事や個室利用など、本人が希望して選ぶ特別なサービスについては、引き続き自己負担となる見通しです。
今後、「標準的な出産費用」に含まれる具体的な範囲について、国が整理を進めていく予定です。
出産費用の無償化が推進される背景
出産費用の原則無償化が進められる背景には、主に「少子化対策」「出産にかかる経済的負担の軽減」「地域格差の是正」という3つの大きな社会的課題があります。
ここでは、それぞれの背景について詳しく解説します。
1. 少子化対策の強化
日本では出生数の減少が続いており、少子化が社会全体の課題となっています。
政府は「こども未来戦略」などで出産・子育て支援の強化を掲げ、特に若年層やひとり親世帯から「出産費用が高くて子どもを持てない」「お金の心配で二人目を諦めた」といった声が多く寄せられていました。
出産費用の無償化は、子どもを持ちたいと望む人が出産しやすい社会を目指す、少子化対策の一環と位置づけられています。
2. 経済的負担の軽減
出産にかかる費用は、現行制度ではほとんどが公的医療保険の対象外となっており、代わりに「出産育児一時金」として50万円が支給されています。
しかし実際の出産費用は、地域や医療機関によって差があり、50万円を上回るケースも多く、さらに年々その費用は上昇傾向にあります。
そのため、出産費用は多くの家庭にとって、経済的負担となっているのが現状です。
無償化により家計の負担を軽減し、安心して妊娠・出産に臨める環境を整えることが目的です。
3. 地域格差の是正
出産費用には地域差が大きく、特に都市部や設備の充実した医療機関では高額になる傾向があります。
例えば、東京都の平均出産費用は約62.5万円、熊本県では約38.9万円と、大きな差があることが分かっています。
地域格差の中でも、どこで出産しても安心できる環境を整えるためには、全国一律で「標準的な出産費用」を公的保険や公費でカバーする制度が求められていました。
そのため、2026年度を目途に、標準的な出産費用の自己負担を原則無償化する方針を固めたのです。
出産費用無償化による病院側の問題
出産費用の無償化が実現すれば、妊産婦にとっては経済的負担の大きな軽減につながります。
一方で、出産を取り扱う病院や産院にとっては、制度変更による経営面での影響が問題となります。
診療報酬制度への移行による収入減の懸念
現在、日本における出産は自由診療として位置づけられており、医療機関ごとに独自の価格設定が可能です。各施設は人員配置やサービス内容に応じて柔軟に価格を設定し、収益を確保してきました。
しかし、無償化によって出産が保険診療の扱いとなると、診療報酬制度に基づいた統一的な料金体系が適用されることになります。
これにより、医療機関は自由に価格を設定できなくなり、特に高品質なサービスで差別化を図ってきた都市部の民間病院では、収益の減少が懸念されています。
サービス縮小と人員削減による医療の質の低下
診療報酬による収入が従来よりも低く抑えられる場合、病院側は経営の見直しを迫られ、コスト削減を余儀なくされる可能性があります。
その結果、助産師や看護師の配置数、24時間対応体制、入院時のケアサービスなどが縮小されるおそれがあります。
産後ケアや母乳外来など、これまで保険外で手厚く提供されてきたサービスの継続が困難になるケースもあるでしょう。
そのような状況が進めば、分娩に関する医療の質が全体的に低下するリスクがあると指摘されています。
地方における分娩施設の減少と地域格差の拡大
出産費用の無償化によって医療機関の収入が減少すれば、小規模な施設では分娩の取り扱いを中止する動きが広がる可能性があります。
実際、分娩を取り扱う医療施設の数は、平成8年には病院1,720施設・診療所2,271施設の計3,991施設でしたが、令和3年には病院946施設・診療所999施設となり、合計で1,945施設にまで減少しています。
20年以上にわたって、一貫して減少傾向が続いているのが現状です。
とくに地方では、もともと産科施設の数が限られているため、さらに施設が減少すれば、妊産婦が分娩可能な医療機関まで長距離を移動せざるを得ないケースが増えることが予想されます。
参考:周産期医療の体制構築に係る指針‐厚生労働省
病院ができる備え
制度変更に伴う不安やリスクを最小限に抑えるためには、医療機関側での事前の準備が重要です。
ここでは、出産費用の無償化に向けて、病院が今から取り組むべき具体的な備えをご紹介します。
制度変更に備えた情報収集
最も重要なのは、政府や関係団体からの最新情報を継続的に収集することです。出産費用の無償化については、現在も厚生労働省を中心に制度設計が進められています。
今後、診療報酬の細則や対象範囲、施設基準などが段階的に公表されていく見込みです。
医療機関としては、公式発表に加え、学会・業界団体が主催するセミナー・説明会にも参加し、制度の動向をタイムリーに把握しておく必要があります。
また、行政による補助金制度や移行支援策が設けられる可能性もあるため、その対象条件や申請のタイミングについても確認しておくことが重要です。
自費サービスの整理と明確化
無償化の対象は、基本的な分娩医療に限られる見込みです。
個室利用、特別食、産後のアロマケアや母乳相談など、本人の希望による付加的なサービスは、引き続き「自費扱い」となる可能性が高いでしょう。
そのため、病院・産院では、自施設が提供している自費サービスの内容と料金を、体系的に整理しておくことが求められます。
将来的には、「基本サービスは無償、オプションには追加費用がかかる」といった説明が必要になるため、分かりやすい料金表やパンフレットの作成も検討しておくとよいでしょう。
職員教育
制度が変更されれば、会計処理やカルテ入力など、業務の流れにも変更が生じる可能性があります。
そのため、看護師・助産師・受付・医療事務など、すべての職種に対して新制度に対応できる教育体制を整えることが必要です。
特に、制度の概要や無償対象の範囲、妊産婦からよくある質問への対応例などについては、定期的な院内研修を通じて周知しておくと安心です。
また、会計や医事業務を担当する職員には、新制度に対応した請求業務や診療報酬点数の理解が求められます。そのため、外部の研修機関やソフトウェアベンダーとの連携を図り、適切なサポート体制を構築しておくことも大切です。
会計業務の効率化と自動精算機の活用
出産費用の無償化により、「公費でカバーされる費用」と「自費負担が残るサービス」が明確に分かれます。そのため、会計時の説明や処理が複雑になり、職員の業務負担が増加することが予想されます。
業務負担を軽減する手段として、自動精算機の導入が有効です。
自動精算機は、保険と自費の内訳をわかりやすく表示し、スムーズに決済できる仕組みとなっており、妊産婦の不安軽減や職員とのトラブル回避にもつながります。
さらに、受付の混雑緩和やミスの削減といった効果も期待でき、制度変更後の新しい運用体制を支える実務的なツールとして注目されています。
まとめ
出産費用の無償化は、社会全体で出産を支えるという理念のもとに進められている重要な制度改革です。
これまで自由に設定できていた料金体系が診療報酬制度へと組み込まれ、収益構造の変化や、人員体制・サービス内容の見直しが必要となるでしょう。
変化に備えるためには、最新情報の収集、自費サービスの整理と説明体制の整備、そして職員への研修・教育が欠かせません。
また、制度変更後の会計業務を円滑に行うための対策として、自動精算機の導入も有効です。
自動精算機の導入をご検討中の方は、ぜひお問合せください。
『Robo Clerk』は使いやすい画面設計と万全のサポート体制で、多くの医療機関から選ばれています。
導入に関するご相談やデモのご希望など、お気軽にお問い合わせください。
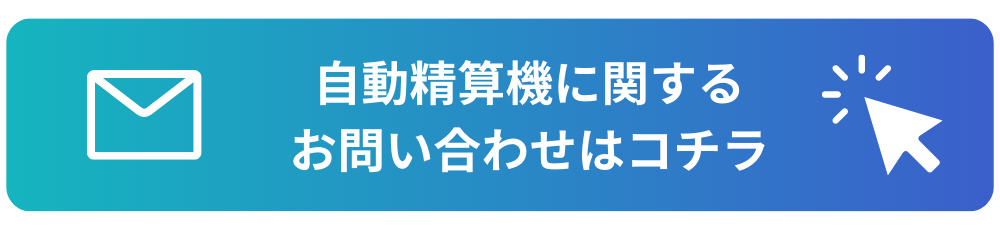
この記事の執筆者
株式会社APOSTRO
マーケティング担当T.O
約5年間の海外暮らしを経験し、某広告代理店で海外の現地法人責任者となる。部分最適に拘る日本の生産性向上に疑問を持っていたところ、「働き方を変える」というテーマを熱く語るAPOSTROに共感し、自らが社会実装役になることを決意し参画中。
自動精算機の導入と合わせてセキュリティ対策を検討したい方は
是非お問い合わせフォームからお問い合わせお待ちしています。
